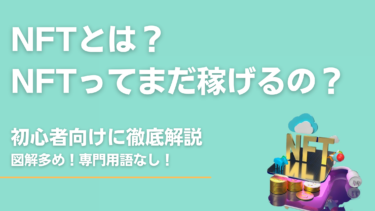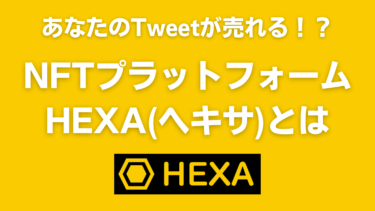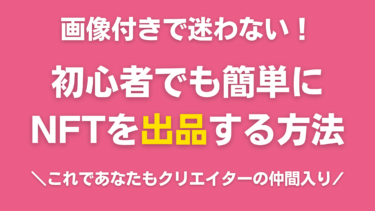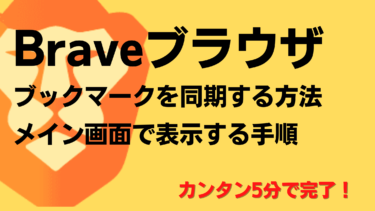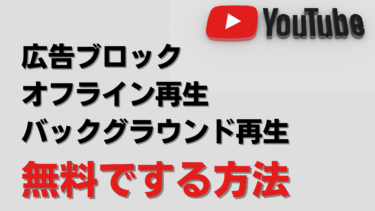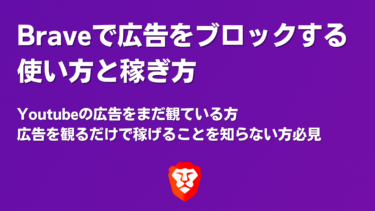今回は最近話題の”DAO”(ダオ)について解説していきいます。
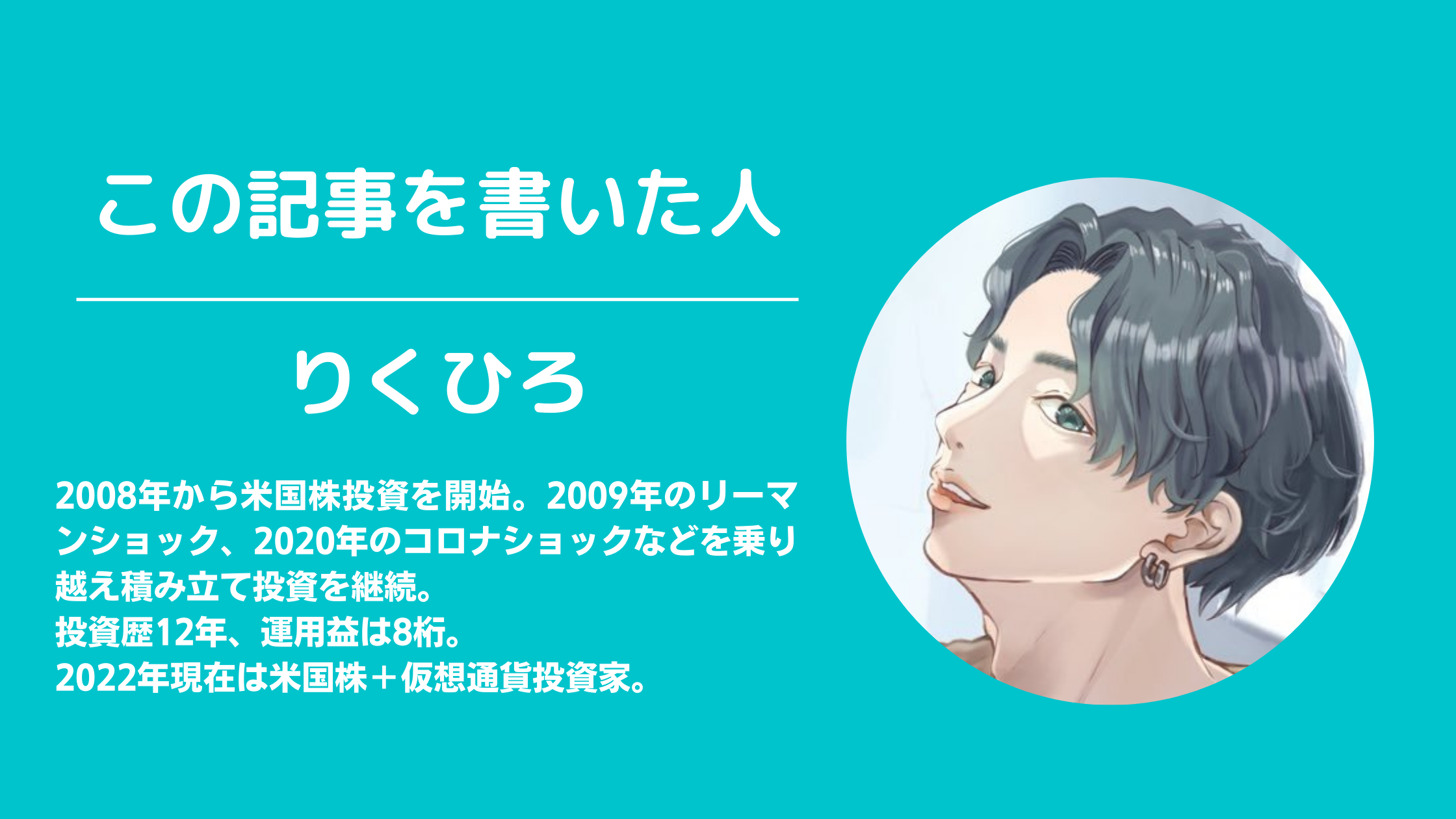
- DAOの仕組み
- DAOが生まれた目的
- DAOのメリットデメリット
- DAOで働く・稼ぐ方法
- DAOの実現性
ちなみに、DAOは「自律分散型組織(Decentralized Autonomous Organization)」の略称です。
DAOの仕組みを簡単に
DAOの初心者向け解説

DAOはWeb3.0時代にくると言われている“新しい組織の仕組み”です。
DAOがどのように新しいかを解説します。
いまの会社には必ずある社長や経営陣、役員ポジションなどがいない組織です。
その代わりに、あらかじめ決められたルールのもとに組織のメンバー皆んなで意思決定していきます。
特定の強い意思決定者がいなくても組織が成り立つ理由は、DAOがブロックチェーン技術をベースにした組織だからです。
このブロックチェーン技術を使い、最初に決めた意思決定のルールを誰でも見えるようにして、自動で実行することができます。
従来型の組織とDAOの仕組みを比べると、このような違いがあります。
ざっくり要点を掴んでみてください。
| 従来型組織 | DAO |
|---|---|
| 階層的・中央集権的 | 分散的 |
| 強いリーダーが意思決定 | 参加者が意思決定 |
| 株主がいる | 株主はいない |
| 参加に制限がある | 誰でも参加できる |
| 固定給が存在する | 貢献度に応じて報酬が決まる |
| 権限のある人間がルールを管理 | 決められたルールで自動的に実行 |
| 活動は非公開で透明性が低い | 活動は公開され透明性が高い |
最も一般的なDAOは、NFTプロジェクトの立ち上げや運営に使われるDAOです。
DAOのメンバーにはNFTが配られたり、そのNFTがDAOの中の特定のコミュニティへの会員権のような役割をもつこともあります。
NFTについてはこちらもご参考に。
» まだ間に合う!NFTアートの始め方完全ロードマップを図解
DAOの目的、なぜDAOは生まれたのか
そもそもDAOはなぜ必要なのでしょうか。
DAOの目的を一言で言うと“中央集権的なリーダーシップの排除”です。
DAOは現代の組織の課題感から生まれた
株式会社は実に400年前に生まれた仕組みと言われており、当たり前にこの構造が使われてきました。
これまでの株式会社に多く見られる階層的・中央集権的な組織では、少人数の経営陣が意思決定します。
しかし、意思決定に関わっていない多くの人にとって、その意思決定に十分な説明がされることは少なくプロセスも不透明です。
結果的に組織内で利害関係や”目的のズレ”が生じてしまう問題がありました。
DAOはここに課題感を持ち、新しい組織のかたちを提唱します。
DAOは一人一人のメンバーが誰かの部下ということはなく、自律した個人として意思決定に参加することでこの問題を解決しようとします。
これまで当たり前に使われていた組織のあり方、リーダーの在り方を根本的に変えることがDAOの目的です。
権力の分散、Web2.0からWeb3.0時代へ
権力の分散も、DAOが作られた大きな目的の一つです。
現代はWeb2.0の時代と呼ばれています。
Web2.0時代を代表するのが、GAFAを中心とした巨大に成長したIT企業、ビッグ・テック企業です。
Googleがあったお陰で私たちは無料で色んな情報を知ることができます。Facebookがあったお陰で遠くの友人とも毎日会話することができます。
これらのIT企業のお陰で私たちの生活が劇的に豊かになったことは間違いありません。
しかしその一方で、GoogleもFacebookのプラットフォームも、ユーザーの提供するコンテンツがなければここまで大きく成長することは出来なかったはずです。
コンテンツを提供される側であるプラットフォーマーが大きな権利と利益を得てきたのに対し、ユーザーにはあまりインセンティブがありません。
そこで、これからはユーザーが運営に参加し、インセンティブがある仕組みにシフトしていこうというWeb3.0の考え方が生まれました。
DAOは特定の誰かが権力を持ちすぎるWeb2.0に課題感を持ち、みんなで分散して運営・管理するWeb3.0時代の新たな組織のかたちなのです。
Web3.0についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
デジタルコミュニティへの需要
手触り感のある人と人との繋がりを取り戻すことにも、DAOは役立っていると考えることができます。
特にコロナ禍において、リアルでの人との繋がりが分断してしまいました。
そのような中で人は孤独感や承認欲求、人との繋がりを求めデジタルの中に新しいコミュニティを求めました。
技術の発展ももちろんですが、コロナがあったからこそDAOがここまで話題になったと考えることができます。
DAOの例
現在の主流なDAOはDeFiと呼ばれる金融分野に多く存在します。
しかし、DAOの目的は様々です。
変わったところでは憲法DAOというDAOもあります。
これは2021年11月のわずか5日間で、サザビーズのオークションで合衆国憲法の原本を購入する目的で始まったDAOです。
最終的にオークションで落札することは出来ませんでしたが、実に4700万ドルを調達することに成功しました。
他にもチャリティーを目的としたDAOや、NFTに共同投資するDAOなどもあります。
NFTについてはこちらに詳しく解説しているのでご参考にしてください。
DAOの特徴とメリット
- 人為的ミスや偏った意思決定を防げる
- 世界中誰でも参加できる
- 圧倒的な生産性を可能にする
- 機会の不平等を解消できる
人為的ミスや偏った意思決定を防げる
DAOの最大の特徴は、一極集中の権力を持つリーダーがいないという点です。
その代わり、プロジェクトのメンバーが意思決定に参加していきます。
ここで大事になるのがガバナンストークンと呼ばれる投票権の存在です。
ガバナンストークンはDAOが発行する暗号通貨であることが多いです。
意思決定に参加したいメンバーはこのガバナンストークンを手に入れて投票します。
従来の組織では声の大きいリーダーの意見が通ってしまうリスクがあります。
一方、DAOでは複数のメンバーが意思決定に関わるため偏った意思決定を避けることができます。
また、ここでなされた意思決定の過程は誰でも見ることができます。
このように透明性を確保することができるのも従来型組織との大きな違いです。
世界中誰でも参加できる
DAOに参加するには履歴書も学歴も必要ありません。
インターネットに繋がってさえいれば、世界中誰でも参加することができます。
また、これまでの株式会社の組織では入社手続き、配属、給与体系など非常に煩雑な手続きが必要でした。
DAOではこのような手続きも非常にシンプルです。
そもそもDAOでは、DAOの立ち上げ初期に決められるスマートコントラクトと呼ばれる運用ルールがあります。
このスマートコントラクトはブロックチェーン上にあり、誰でも見ることができ自動で実行される仕組みです。
スマートコントラクトがあるお陰で、DAOは煩雑な手続きもなく世界中から誰でも参加できる仕組みになっています。
圧倒的な生産性を可能にする
現代の社会組織では、階層的な組織構造によって個人の思考や能力が最大限引き出されないケースがあります。
一方、DAOは共通の目的を持ったプロジェクトに参加者が集まります。
そして参加者の貢献する度合いに応じてインセンティブがあるように設計することで、個々のアイデアを最大化し生産性を高めることが可能です。
機会の不平等を解消できる
現実世界ではあり得ませんが、DAOでは完全に匿名かつ姿を晒すこともなく参加することができます。
またDAOに参加する前提として、性別や国籍、更には年齢も関係ありません。
身体的な障害も、ツールさえ使えれば関係ありません。
DAOの中では全ての人に機会が平等に与えられます。
つまりそれは、昨今叫ばれているダイバーシティ(多様性)やインクルージョン(包括性)が真の意味で保たれることを意味します。
DAOのデメリットと実現性
現在最大級かつ長期で持続しているDAOはビットコインのプロジェクトと言われています。
ビットコインは発明者と言われるサトシナカモトというリーダーがいなくても、世界中の人がプロジェクトに参加し運営が続けられています。
では、全ての組織はDAOにしていけば良いのでしょうか。
ここからはDAOのデメリットと実現性について解説していきます。
DAOのデメリット
まだまだ新しいDAOには、デメリットも多いのが現実です。
- 法律が追いつかない
- セキュリティの強化が必要
- インセンティブが持続しない
- 投票時の力関係
- 意思決定スピードが落ちる
- リソースの配分が難しい
法律が追いつかない
現状の日本の法律では、トークンによる資金集めが税制上非常に難しいです。
また、消費者保護の視点でもまだまだ脆弱です。
例えば、DAOでよくあるケースであるDeFi(分散型金融サービス)では、数億円規模でのハッキングが起きています。
被害額を補填する法律はなく参加者は泣き寝入りせざるを得ません。
DAOが普及していくためには、消費者保護法や税制の整備が必要です。
セキュリティの強化が必要
上記にあげたハッキング問題では、ハッキングされないための対策も必要です。
2016年、自律分散型投資ファンド「The DAO」がハッキングを受け総資金の約3分の1である約50億円が不正流出してしまいました。
最終的に不正流出した分は無効化することができましたが、DAOのセキュリティ面での脆弱性が露呈された事件になりました。
インセンティブが持続しない
DAOは比較的少人数のケースでは効率的です。
しかし、DAOが組織として成長し参加人数が増えてくると、DAOの貢献に関心のない人もたくさん入ってきます。
すると新たな問題が発生します。
彼らはDAOに貢献したいというより、自分の短期的な利益が目的であったり、ただ見ているだけであることが多いのです。
このようなフリーライダーが増殖すれば、本当にDAOに貢献しようとしている人にも影響が出てきます。
こうした形でDAOが形骸化してしまうケースは少なくありません。
投票時の力関係
DAOの特徴として、ガバナンストークンを使った投票で意思決定をすることが可能というお話をしました。
これは1人の強いリーダーが全て決めてしまうことによる利害関係や目的のズレを防ぐ上では非常に有効です。
ただしこれも完璧な解決策ではありません。
例えば、ある人が多額の資金を投下し大量のガバナンストークンを保有できるとします。
ガバナンストークンの保有比率が高いほど投票に与える影響も大きくなれば、結局はこの保有比率の高い人の力が強くなりすぎてしまいます。
意思決定スピードが落ちる
組織運営では、時に重要な意思決定を迅速にしなければならない場面もあります。
また問題が複雑であればあるほど柔軟性も問われます。
世界中に参加者がいるDAOにおいて、このようなケースで迅速かつ柔軟な意思決定をするのは非常に困難です。
全ての回答が集まる前に意思決定できる仕組みにすることも可能です。
しかしその一方で、本来のDAOの意義がやや損なわれてしまうリスクがあります。
リソースの配分が難しい
『パーキンソンの凡俗法則』をご存知でしょうか?
これは「組織が重要な課題よりも些細な課題に時間と労力を割いてしまう」という主張です。
例えば組織にとって有益な技術のアップデートの議論をするのか、皆んなで集まる楽しいイベントの企画に時間を使うのか。
どちらかと言うと楽しい企画に時間を使ってしまいがちです。
個人の行動が制約されないDAOでは、この現象が起きやすく結果的に生産性が下がってしまうリスクがあります。
現実的なDAOの仕組みを考える
初めから完全に公平なDAOをつくることは非常に難しいです。
なぜなら、立ち上げ初期には思想が固まっていない状態で意思決定すべき場面が多いからです。
従って、初期の一定期間は中心人物が意思決定せざるを得ない場面が多くなります。
また、組織としても未熟な最初の資金集めには、会社として株式などで資金を集めるのが現実的です。
後々サービスが軌道に乗ってきたらトークンを発行し、コミュニティに還元しながら徐々にDAO化を目指していきます。
ただし、この場合にも組織全体がDAOになる、というよりは、あるプロジェクトが「DAOの要素を取り入れている状態」となる組織が多いことが予想されます。
DAOに向く組織
DAOが素晴らしい仕組みをもつ組織体系だとしても、全ての組織がDAOになることは考えづらいです。
なぜなら、DAOに向く組織と向かない組織があるからです。
DAOに向く組織
DAOに向く組織は、オペレーションがシンプルで、グローバルにニーズがある事業です。
今最も主流となっているDAOは、DeFi(分散金融)です。
DeFiは複雑なパラメータ調整や技術的アップデートが頻繁に行われます。
しかし、この分野はオペレーション自体はシンプルであるためDAOに向いていると言えます。
DAOに向かない組織
反対にDAOに向かない組織もあります。
例えば営業、カスタマーサポートのように、人の感情など複雑でパターン化できない業務は不向きと言えます。
また、当然ですが物理的な接触が不可避なサービス業もDAO化が難しい分野になります。
DAOの働き方
DAOの参加者は基本的にオンライン上で匿名で活動します。
DAOのコミュニケーションは現状、Discordと呼ばれるツール一択と言えます。
Discord上では、参加者の貢献度が可視化されます。
また、DAOの組織はフラットと言っても完全にフラットではないことが多いです。
貢献度やスキルに応じてプロジェクトごとに「メインコントリビューター」と呼ばれるメンバーが存在します。
これは権限の差というよりは、役割の違いと言えます。
コアコントリビューターが出した選択肢に対し、他のコントリビューターが反応する形で業務は進んでいきます。
DAOに向く人向かない人
これまで述べてきた通り、基本的に誰でもDAOに参加することは可能です。
ただし、DAOに向く人と向かない人がいることは確かです。
DAOでは指示待ち人間は少ない
例えば、“指示待ちの人”はDAOにはあまり向きません。
DAOの中では指示する人、指示される人という関係ではないため、自主的に行動ができないと難しいかも知れません。
指示を待っているだけだと仕事は発生せず、指示待ちの人は参加するインセンティブが減りだんだんとその数は減っていきます。
DAOでは尖った人材が重宝される
何となく平均的な能力の人よりも、出来ないこともあるが尖った能力がある人の方が向いています。
つまり、DAOではそれぞれが自分の”好き”や”得意”を活かせる方が重宝されます。
反対に、誰でも出来る仕事をこなすだけの人は、DAOでは活躍の場が限られてきます。
なぜなら、誰でもできるような仕事は自動化されるか低単価で外注、もしくはAIに任せることができるからです。
何を安定と考えるか
DAOには労働時間に応じた固定給は基本的にありません。
また、貢献度によって報酬が決まるので、実力主義の考え方でバリバリやりたい方には向いていると言えます。
「自動で給料が振り込まれるのが安定」と思っているとDAOで働くのは辛くなります。
むしろどこでも活躍できるスキルを身につけることが、DAOの普及する世界では安定と言えます。
DAOの未来
これからは一つの企業にコミットするという働き方から同じ目的を持ったメンバーでプロジェクトベースで働くことになるかも知れません。
そして、複数のプロジェクトに関わることも当たり前になるのではないでしょうか。
おそらく今のWeb2.0の組織がなくなることは考えづらいです。
しかし、Web2.0企業で働く比重を落としながらWeb3.0のDAOで働く未来は想像ができます。
世界中の人と繋がり働けるようになることは、自国経済が行き詰まっている国にとって大きなチャンスではないでしょうか。
人生100年時代と言われるなか、このDAOという組織と働き方を知っていることが大きな差になることは間違いなさそうです。
現実世界とどこまで繋がるかは分かりませんが、これからはDAOに働く場所がある人とない人では圧倒的な差が生まれると考えられます。